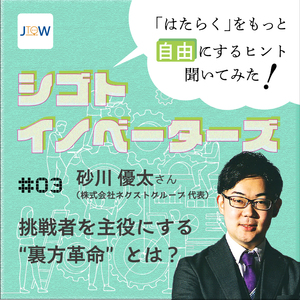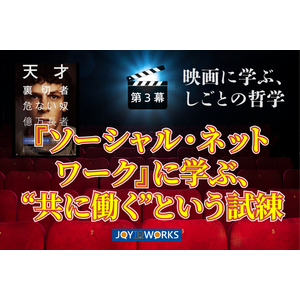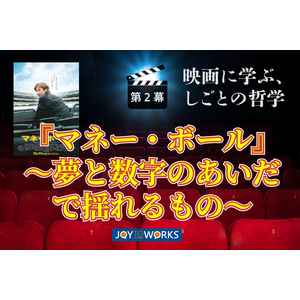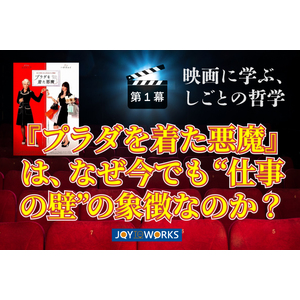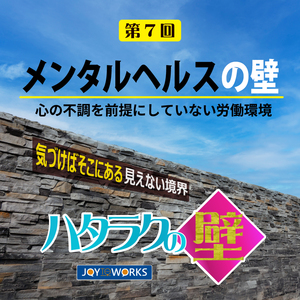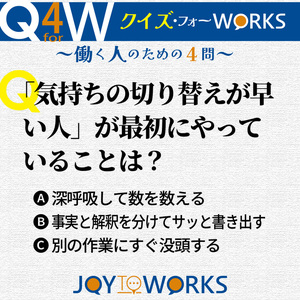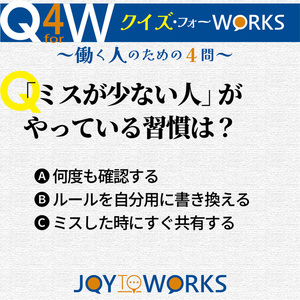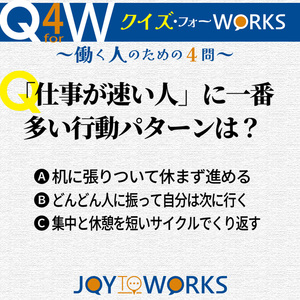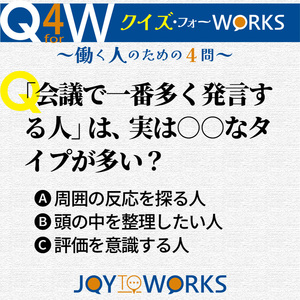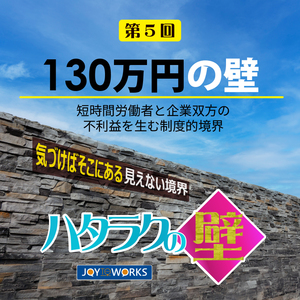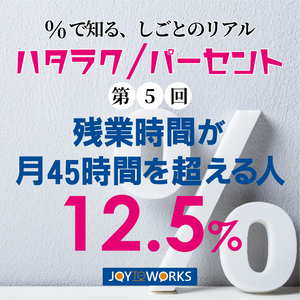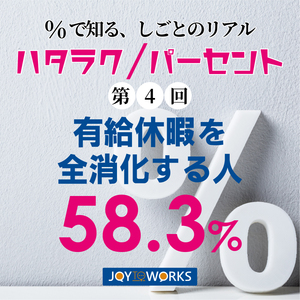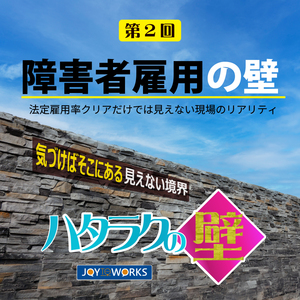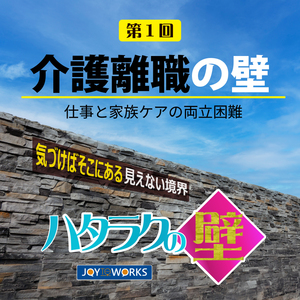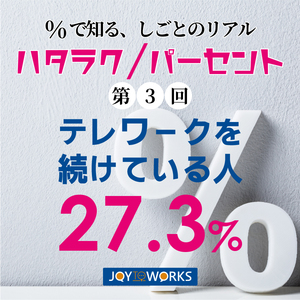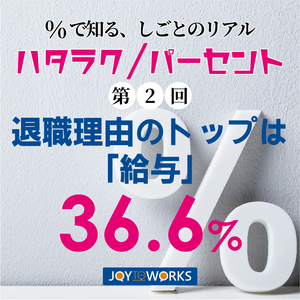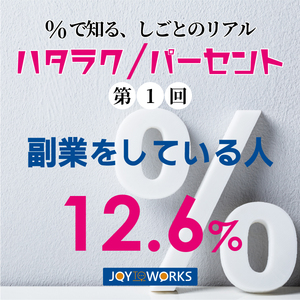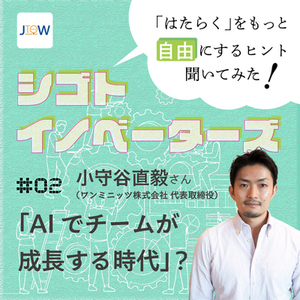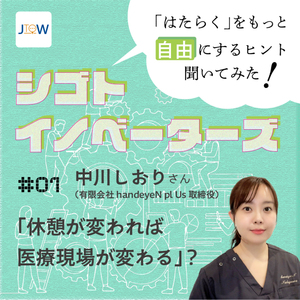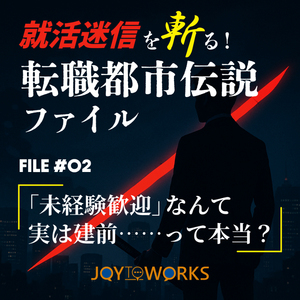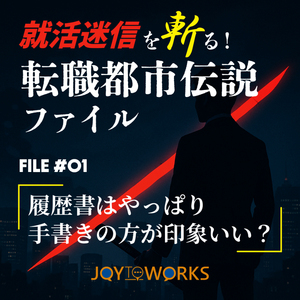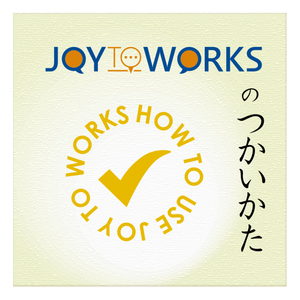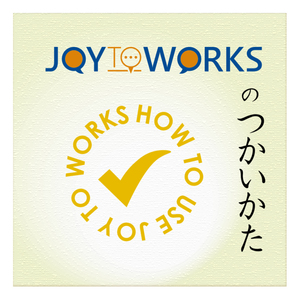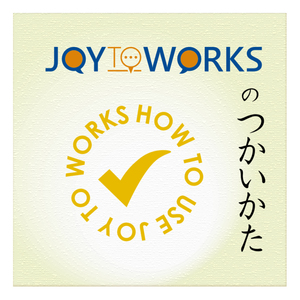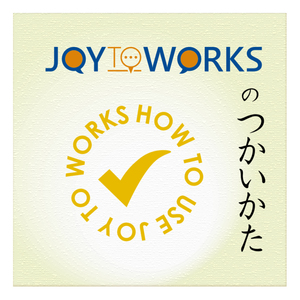ここでいうブランクとは、一定期間、就労が途切れた状態を指します。本来は“何もしていなかった時間”ではありませんが、履歴書の一行だけでは伝わらず「説明できない空白」と見なされやすい構造があります。この「事実そのもの」よりも、「どう解釈されるか」が壁をつくる要因です。

気づけばそこにある"見えない境界"
ハタラクの壁
働く人生のどこかで、キャリアが途切れてしまう時期は誰にでも訪れます。子育て、介護、病気、メンタル不調、転職活動の長期化──理由はさまざまですが、ブランクが長くなるほど「もう戻れないのではないか」という不安が大きくなりがちです。企業側もまた、即戦力採用のニーズが強いほど、ブランクのある応募者に慎重になりやすく、双方の不安が重なって“見えない壁”が生まれます。今回のテーマは、その構造に迫る「ブランクの壁」です。
ここでいうブランクとは、一定期間、就労が途切れた状態を指します。本来は“何もしていなかった時間”ではありませんが、履歴書の一行だけでは伝わらず「説明できない空白」と見なされやすい構造があります。この「事実そのもの」よりも、「どう解釈されるか」が壁をつくる要因です。
ブランクが問題化する背景には、働く人自身・採用する企業・社会制度のそれぞれにある“解釈のズレ”が静かに積み重なっています。本人は空白に不安を感じ、企業は情報不足ゆえに判断を慎重にし、社会の仕組みは連続したキャリアを前提に作られている――この三者が噛み合わないことで、本来は価値があるはずの期間が過剰にネガティブに扱われてしまうのです。
本人
企業
制度・社会
ブランクの壁は、個人の努力不足や企業の冷たさだけで生まれるものではありません。社会構造そのものが、空白を過剰に不安へ変えてしまう仕組みになっています。
ブランクを不利にしないためには、本人・企業・制度のどれか一つが頑張るのではなく、三つの側面が“空白を正しく扱う仕組み”を共有することが大切です。働く人は空白を経験として言葉にし、企業はその価値を理解し受け止める枠組みを持ち、社会は再スタートを支える情報と支援を届ける。こうした連携が進むことで、ブランクを「弱み」ではなく「経験」として扱える構造に変えていくことができます。
本人ができること
企業ができること
制度・第三者が担えること
ブランクの壁は、「働いていなかった時間」が問題なのではありません。その時間をどう見るかというレンズが古いままであることが、本当の壁です。空白をマイナスではなく、「そこにあった経験」として丁寧に見つめ直すこと。企業が“非連続のキャリア”を前提に採用設計を見直すこと。これらの視点の更新によって、ブランクは「途切れたキャリア」ではなく、「働き続けるための経験」へと変わっていきます。