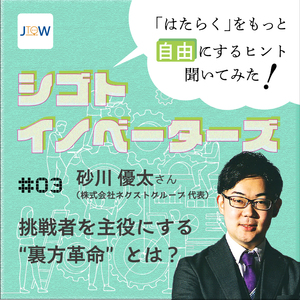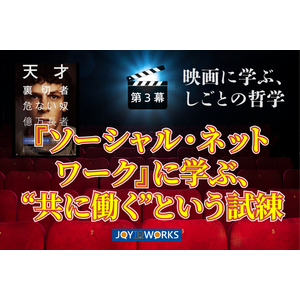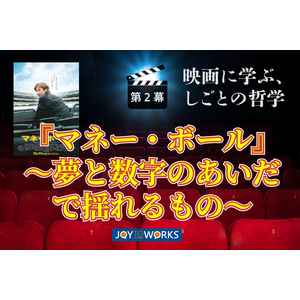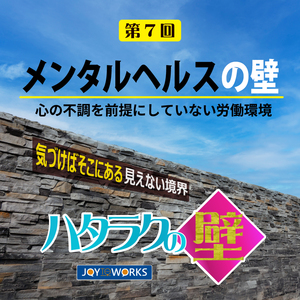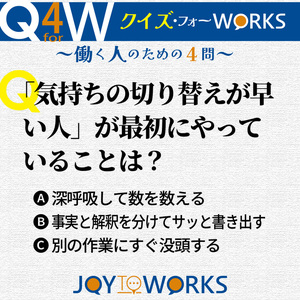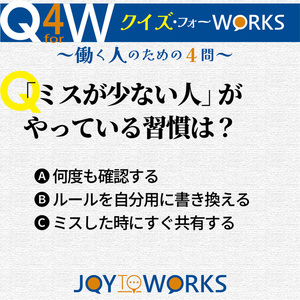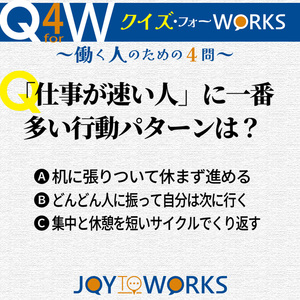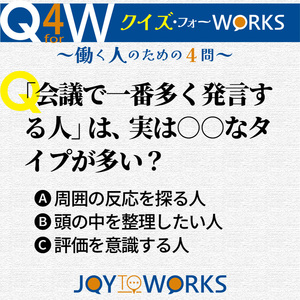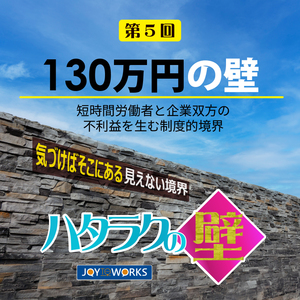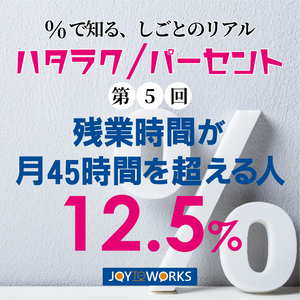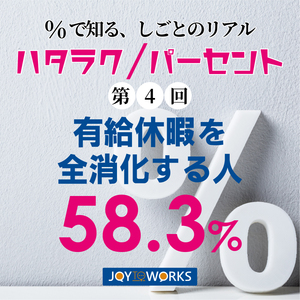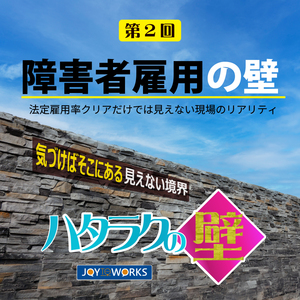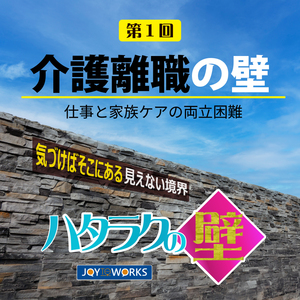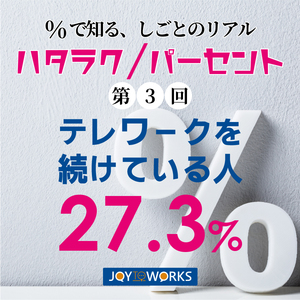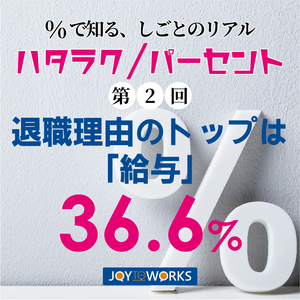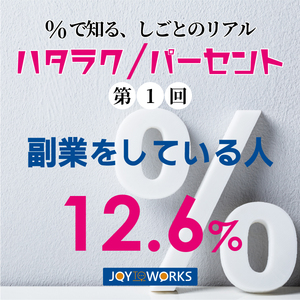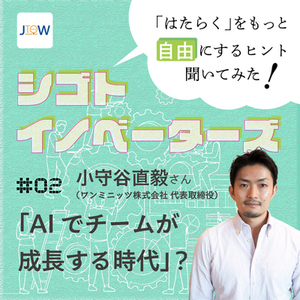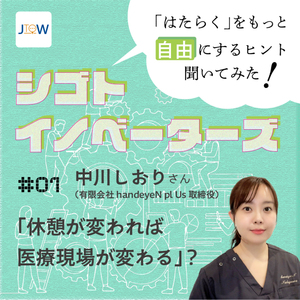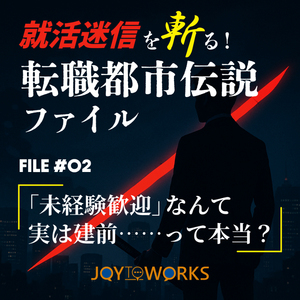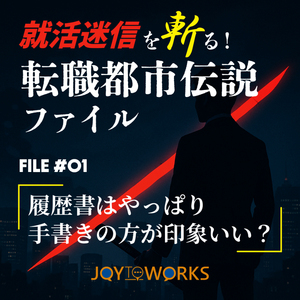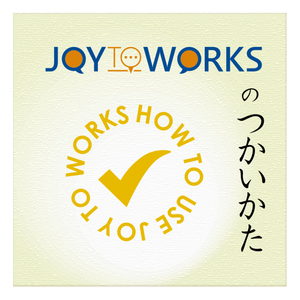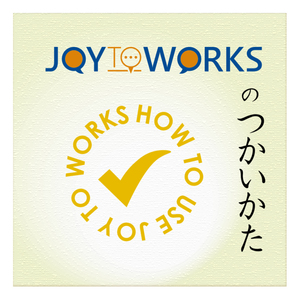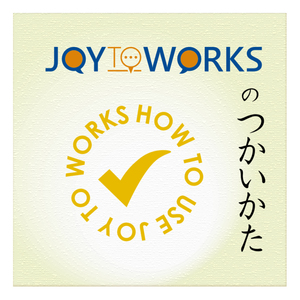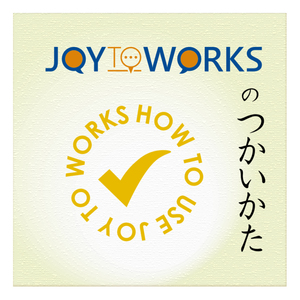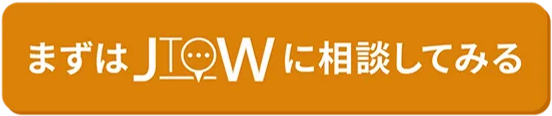『プラダを着た悪魔』は、働く人が必ずぶつかる壁――「これまでの努力や価値観が、突然通用しなくなる瞬間」を真正面から描く作品だ。
主人公アンディ(アン・ハサウェイ)は新卒のジャーナリスト志望で、ファッションにはほとんど興味がない。だが面接当日の朝、彼女なりに精一杯身だしなみを整え、必死に準備してランウェイ編集部に向かう。ところが、その“努力”はファッション誌の世界では努力にすら見えなかった。場違いな格好でオフィスに入った瞬間、冷ややかな視線が一斉に向けられる。
そして編集長ミランダ(メリル・ストリープ)は、アンディの必死さを一瞬で見抜きながらも淡々と言い放つ。「あなたの努力なんて、私には関係ないわ」。これはアンディが「努力したのに」と主張したわけでも、反論したわけでもない。むしろ、アンディが“努力しているつもり”であることが、ミランダには透けて見えていた。努力の方向が違えば、それは努力として評価されない。映画は冒頭からこの分厚い“壁”を観る者へ突きつける。
主人公アンディ(アン・ハサウェイ)は新卒のジャーナリスト志望で、ファッションにはほとんど興味がない。だが面接当日の朝、彼女なりに精一杯身だしなみを整え、必死に準備してランウェイ編集部に向かう。ところが、その“努力”はファッション誌の世界では努力にすら見えなかった。場違いな格好でオフィスに入った瞬間、冷ややかな視線が一斉に向けられる。
そして編集長ミランダ(メリル・ストリープ)は、アンディの必死さを一瞬で見抜きながらも淡々と言い放つ。「あなたの努力なんて、私には関係ないわ」。これはアンディが「努力したのに」と主張したわけでも、反論したわけでもない。むしろ、アンディが“努力しているつもり”であることが、ミランダには透けて見えていた。努力の方向が違えば、それは努力として評価されない。映画は冒頭からこの分厚い“壁”を観る者へ突きつける。